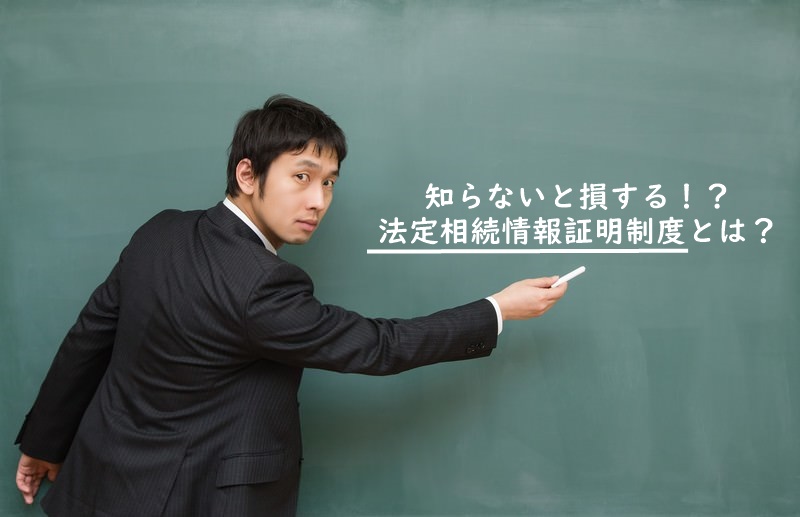
従来の相続では、あらゆる手続きにおいて誰がいつ亡くなったのか、相続人は何名なのかなどを証明するため、各窓口において戸籍や住民票などを提出しなればなりませんでした。
しかも、窓口によってはコピーでも認められる場合もあれば、原本しか認めない窓口もあるなど、最終的にどれだけの証明書が何通必要なのかが分からず相続人にとっては大きな負担となっていました。なかにはたくさん余ってしまったり、反対に足りなくなって再度手配しなければならなかったという方もいらしゃることでしょう。
一方で、相続人から提出された戸籍などをチェックする金融機関などの相続担当部署にとっても、複数の書類を照らし合わせて事実確認するのは大変な作業です。
そこで、相続人や各機関の相続担当部署双方の負担を軽減するために平成29年5月29日からはじまったのが、法定相続情報証明制度です。
これによって、亡くなった事実や家族構成などの情報を一つの書類にまとめることが可能になり、さらに法務局の認証によってその真正性が担保されるようになりました。
同じ戸籍を何通も手配しなければならないといった手間や費用を省略することができるようになったのと同時に、簡素化された正しい情報を読み取ることができるようになったわけです。
とても便利な制度だと思うのですが、残念ながらそれほど世間では知られていないのが現実です。そこで今回は、法定相続情報証明制度について掘り下げてみようと思います。
以前このホームページでは法定相続情報証明制度についてご紹介したのですが、かなりのボリュームとなってしまったため細かい部分までお伝えしきれませんでした。 そこで今回は、補足という意味も含めて法定相続情報証明制度に関する「よ …
法定相続情報証明制度の概要
法定相続情報証明制度の概要は次のとおりです。
- 相続人が法務局に対し次のような必要書類を提出する。
・亡くなった方が生まれてから死亡するまでの戸籍関係の書類
・戸籍関係書類に基づいて作成された法手相続情報一覧図 - 法務局が上記1の内容を確認し、認証文付きの法定相続情報一覧図の写しを交付する。
いくつか補足説明をしていきます。
なお、法務局の資料やホームページでは「登記所」とか「登記官」といったあまり馴染みのないフレーズが使われているので、このページでは分かりやすく法務局としています。
窓口は法務局
前述のとおり、法定相続情報証明の手続きは法務局になるのですが、どの法務局でも構わないというわけではありません。
利用できる法務局は次のいずれかです。
- 亡くなった方の本籍地
- 亡くなった方の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 亡くなった方名義の不動産の所在地
申出人の便宜にために亡くなった方の本籍地や住所地というのは理解できるのですが、なんで名義の不動産の所在地も含まれるのか?と不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
実はこれにはある背景が関係していると考えられます。
法務局では、すでに登記された情報(不動産や法人について)を交付請求する場合は、全国どの法務局でもすることができるのですが、登記申請は対象の不動産や法人が所在する地域を管轄する法務局に対してしなければなりません。 また、法 …
法定相続情報証明制度に背景には相続登記の未了増加!?
法務局の情報では次のようなことが挙げられていました。
- 不動産の所有者が死亡した場合、相続登記が必要だが、近年、相続登記が未了のまま放置される不動産が増加し所有者不明土地問題や空き家問題の一因になっているため、法務局において相続登記を促進するために法定相続情報証明制度を新設。
つまり、もともとは相続登記を促すために始まった制度であると読み取ることができますね。ちなみに、亡くなった方が不動産を持っていなくても法定相続情報制度は利用することができます。
制度のねらいからも相続登記の促進がうかがえる!?
さらに法務局の情報には制度のねらいが挙げられていて、ここからも相続登記を勧めていることがよく分かります。
- 亡くなった方名義の預金の払い戻し等、様々な相続手続に利用されることで、相続手続に係る相続人・手続きの担当部署の負担が軽減。
- 相続人に相続登記のメリットや放置することのデメリットを法務局が説明することなどを通じ、相続登記の必要性について意識を向上。
相続登記は令和5年現在のところ任意なので、2番目の項目はどちらかというと法務局の都合?という感じがしないでもないという印象です。
ちょっと待って!相続登記は義務化される!(令和6年4月1日~)
令和6年4月1日から相続登記が義務化されることになりました。これによって法定相続情報証明制度がより役立つかもしれません。
ちなみに、相続登記をしなければならない期限は、「相続が開始して所有権を取得したことを知ってから3年以内」と定められています。
これにはなんと罰則規定もあって、上記期限までに相続登記をしないと10万円以下の過料が科される可能性があります。相続人にとっては確実に手間が増えることになりますが、一方で司法書士さんは仕事が増えるかもと期待しているかもしれませんね。
申出人となることができる者は誰?
法定相続情報証明の申出をすることができる者は限られていて、基本的には亡くなった方の相続人となっています。そもそも、相続手続きをする際に便利なものですから、手続きを主導していく代表相続人が申出をすることになるかと思います。
もちろん、代理人を選定することができるのですが、代理人の範囲も限られていますのでご注意ください。
- 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人)
- 民法上の親族(配偶者、6親等内の親族、3親等内の姻族)
- 弁護士
- 司法書士
- 土地家屋調査士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 弁理士
- 海事代理士
- 行政書士
ここで興味深いのが、姻族が代理人として認められているところです。というのは、姻族(配偶者の家族)は相続権がないからです。
相続人が忙しくて対応できない場合などを想定して申出人の範囲を広げたのでしょうか。かなり親切な義理の家族でないとありえないような気もしますが、この点はよく分かりません。
なお、申出は郵送でも可能です。
少なくとも1回は亡くなった方の戸籍などを取集する必要がある
さて、法定相続情報証明制度によって戸籍などの証明書を何枚も手配する必要がなくなったことは間違いないのですが、法務局に提出するために1回は収集しなければなりません。
法定相続情報証明制度では、どういった戸籍関係書類を収集しなければならないのかあらかじめ指定されていますのでご紹介します。
<亡くなった方に関する書類>
・戸籍謄本
・住民票の除籍
<相続人に関する書類>
・戸籍謄本または抄本(死亡日以後のもの)
・申出人の住所氏名を確認できることができる公的書類
(運転免許証表裏のコピー、マイナンバーカード表のコピー、住民票など) ※コピーは原本証明が必要
<状況に応じて必要となる書類>
・各相続人の住民票
・委任状(代理人に依頼する場合)
・資格証のコピー(行政書士等の代理人に依頼する場合)
・亡くなった方の戸籍の附票(住民票の除票がなかった場合)
品目は従来と変わりませんが、1回1通ずつで足りるということです。
このほか申出に必要な書類
申出には上記の戸籍関係書類に加えて、次の書類を提出する必要があります。
- 申出書
- 法定相続情報一覧図
申出書
申出書は交付申請書のようなもので、住民票を請求するときに記入する書類をイメージしていただけばOKです。
様式は次のとおりです。

法定相続情報一覧図
この法定相続情報一覧図が最も難しい部分になるかと思います。
法定相続情報一覧図とは、亡くなった方と相続人とのつながりを示す家系図の縮小版のようなものです。戸籍などの情報を読み取り、相続人側が作成しなければなりません。
「法務局が作ってくれないの?」と思われた方もいらっしゃるかもしれませんが、法務局はあくまで認証を与えてくれるだけです。とはいえ、審査の過程において戸籍情報等と整合性を確認し、もしおかしな点があれば指摘をしてくれると思います。
一般的なご家庭であれば、戸籍などを読み取るのはさほど難しくはないのですが、離婚歴があったり養子に入っていたりすると複雑になってきて読み取りが難しくなってくる可能性があります。
また、現在の戸籍には記載が抜けていて、過去の戸籍(改正原戸籍)にさかのぼらないといけないパターンもあります。
もしご自身では難しいと感じられた場合は行政書士など代理が認められた者に相談してみてください。
ご安心ください!法定相続情報一覧図には様式がある!
家系図というと、皆さんがイメージするとおり線でつないで枝分かれしていく図になるわけですが、これをパソコンで作成するのは難しそうに感じますし、かといって手書きもいかがなものかという気もします。
ご安心ください。法務局ではちゃんと法定相続情報一覧図用の様式が公開されていますので一から作成しなくても大丈夫です。
法定相続情報一覧図を作ってみた!?
法務局の様式を使って、相続人が3人(配偶者+子2人)の法定相続情報一覧図を作成してみました。

戸籍等をきちんと読み取ることができれば、あとは住所氏名などをあてはめていくだけですので、図の作成自体はそれほど難しくありませんでした。むしろ戸籍等を正確に読み取れるかどうかの方が大事だと思います。
様式はエクセルで、少しおかしくなっているところがあったので修正が必要な部分がありました。パソコンが苦手だったり、エクセルを使ったことがない方はつまずくかもしれません。
様式は、この相続人の人数か違うパターンや代襲相続が発生している、養子がいるパターンなど様々なものが用意されています。しかし、様式にないケースは一番近い様式に手を加える必要がありそうです。
困難な場合は列挙形式もある!でも注意が必要!
枝分かれの線で示した家系図タイプの法定相続情報一覧図の作成が難しいという場合、列挙形式という方法もあります。列挙方式とは亡くなった方とその相続人の情報をその名のとおり列挙した様式です。
試しに先ほど作成したものを列挙形式にしてみました。

シンプルで作成自体はしやすいのですが、、列挙形式では異母(父)の兄弟を判断することができないなどの問題点があるので注意が必要です。
これが法定相続情報の証明書だ!
さて、法定相続情報一覧を含め必要書類を法務局に提出すると、審査期間を経て戸籍情報などが集約された次のような証明書が交付されます。

従来の戸籍関係書類に代わって、この証明書を金融機関などの窓口に提出することになるわけです。
証明書は5年間再交付できる
法定相続情報の証明書は、5年間は法務局で保管されていますので、その間何度でも再交付することが可能です。
もし相続の手続きで追加で必要となった場合は、遠慮なく法務局で再交付を受けましょう。なお、再交付には再交付申出書を提出する必要があります。
このとき、法務局は提出された法定相続情報一覧図を基に再交付をしますので、申出をしていない法務局では再交付を受けることはできません。また、当初の申出人しか再交付を受けることはできません。
つまり、再交付は申出人が申出をした法務局のみで可能ということです。ですから、最初の申出は申出人の最寄りの法務局で行った方がよいでしょう。
この点はご注意ください。
まとめ
いかがでしょうか?
かなりのボリュームとなってしまいましたが、法定相続情報証明制度について理解が深まったのではないかと思います。
法定相続情報証明制度は平成29年から開始され、当初はそ利用範囲が限られていたのですが、その後、年金手続きや相続税の申告においても利用できるようになり、その利用範囲が拡大され、ますます便利になりつつあります。
相続手続きは誰もがいつか関わることになります。無視はできでも無関係ではいられません。
ぜひお役立てください。




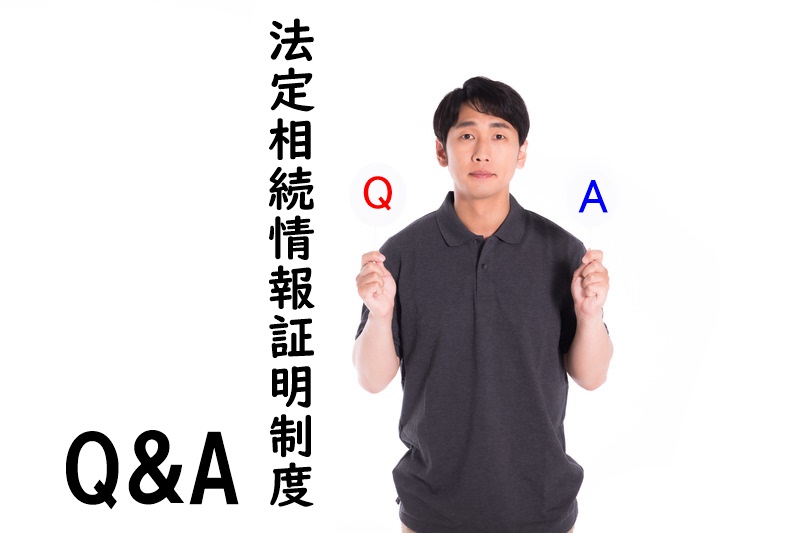
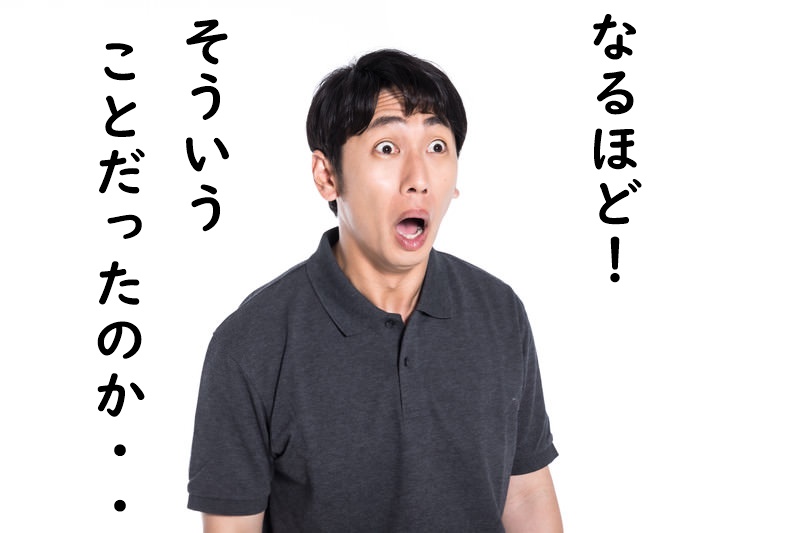
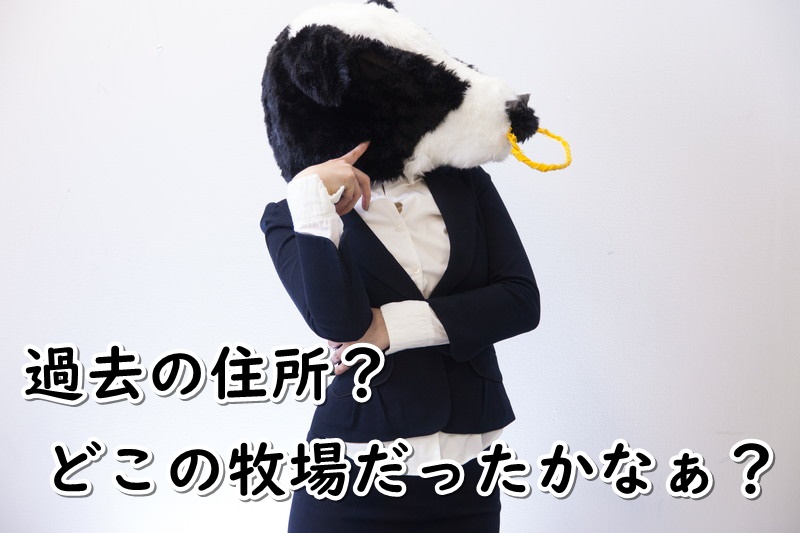
郵送請求できることは知っているんだけれど・・・
ご存じの通り、戸籍や住民票といった証明書は郵送で請求することができます。
郵送請求はどなたでもすることができますから、取得代行など不要なのではないか?と思われる方もしらっしゃるかもしれません。
しかし、郵送請求はたとえ地元の自治体であったとしても1週間程度かかったり、定額子為替といった馴染みのないものを手配しなければならないといった手間もあるため、敬遠される方も少なくないようです。
また過去には、「郵送請求だと進捗がわからないので不安だから誰かに依頼したかった。」という声もありました。
そこで、各種証明書の取得代行サービスを本格的にスタートすることにいたしました。
愛知県外の方だけではなく、平日は仕事で役所に行けない方や、「郵送請求はちょっと面倒だなぁ・・・」という地元の方にもおすすめとなっております。
ぜひご利用ください!
 クリックするとお問い合わせフォームへ移動します。
クリックするとお問い合わせフォームへ移動します。